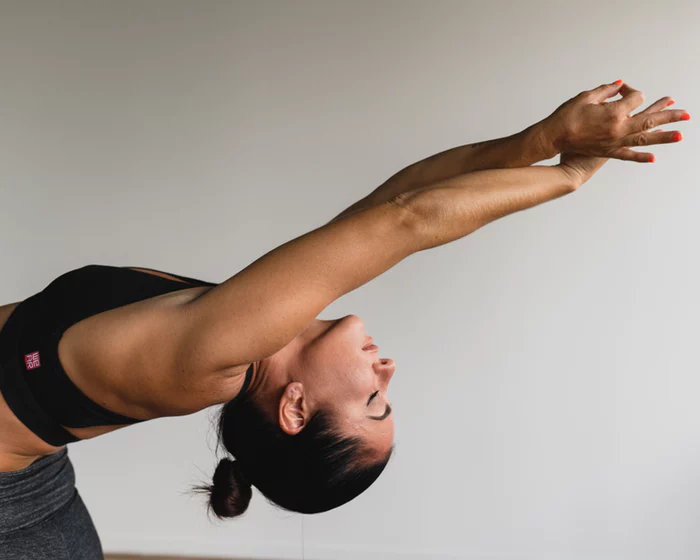ヨガは、ポーズ、呼吸、瞑想からなるといわれており、呼吸はヨガの重要な要素です。
ヨガの呼吸法にはさまざまな種類がありますが、そのなかでも腹式呼吸が基本とされています。
腹式呼吸という言葉は聞いたことがあっても、実際やったことがない、やり方がわからないという人もいるかもしれません。
ヨガの基本となる腹式呼吸はどのようなものか、腹式呼吸がヨガの効果にどのように関係するのかを解説します。
目次
【腹式呼吸と副交感神経のメカニズム】腹式呼吸とは?

腹式呼吸とは、吸うときにお腹がふくらみ、吐くときにはお腹がへこむ状態になる呼吸方法です。
胸は動かさず、お腹が動くのを感じながら行います。
腹式呼吸をすると、肺の下にある横隔膜が上下に動きます。
息を吸う時には横隔膜が下にさがり、息を吐くときには横隔膜が上にあがるという動きです。
腹式呼吸を行うことで、副交感神経の働きが高まって、リラックス効果を得られます。
腹式呼吸がリラックス効果につながる理由を説明します。
腹式呼吸が副交感神経(自律神経)に効くメカニズム

腹式呼吸でリラックス効果を得られるのは、腹式呼吸が自律神経の働きをコントロールするためです。
自律神経は、意識せずとも人間の体の中で働いて、体の機能を保っています。
自律神経には、交感神経と副交感神経というふたつの種類があり、このふたつがバランスをとりあっています。
交感神経は、人間が活動するときに働きが高まり、主に昼間に働いています。
副交感神経は、休息したり、リラックスしたりしているときに働きが高まり、主に夜間や睡眠中に働きます。
どちらも人間にとって必要な働きですが、どちらか一方が優位の状態が続き、バランスがとれなくなると、心身に不調が現れます。
日々を忙しく過ごす中で、過度なストレスにさらされていると、交感神経が優位な状態が続きます。
交感神経が優位な状態だと、呼吸は浅くなります。
呼吸が浅い状態では体に十分な酸素が送れないので、疲れやすい、疲れが取れないという状況に陥りやすいです。
現代社会に生きる私たちは、ストレスが多く、生活リズムも乱れがちです。
これは、交感神経が優位になりやすい状態といえます。
副交感神経の働きが足りておらず、自律神経のバランスが崩れやすくなっているのです。
そのため、副交感神経を働かせるようにする必要があります。
深い呼吸は、意識的に副交感神経を働かせることができる方法です。
深く呼吸をすると、横隔膜が動きます。
横隔膜には自律神経が集中しているので、横隔膜を刺激すると、自律神経が刺激されることになります。
息を吐くときは、副交感神経の働きが高まるので、深く呼吸をすることで副交感神経を働かせてリラックスした状態を作り出せるのです。
ヨガと腹式呼吸の関係

ヨガの基本は、腹式呼吸です。
なぜ腹式呼吸をするかという理由は、ヨガ本来の目的と関係しています。
古来から伝わるヨガの目的は、心身を整え、心と体の安らぎを得ることです。
心と体の安らぎを得る方法として腹式呼吸を取り入れています。
呼吸によって集中力が高まり、リラックスできて心と体が結びつくということです。
ヨガでは、呼吸法のことを「プラーナヤーマ」と呼びます。
プラーナとは、生命エネルギーという意味です。
呼吸によって生きるために必要なエネルギーを取りこむという考え方です。
自律神経のメカニズムなど解明されていなかった古来から、腹式呼吸が心身の健康につながることがわかっていたのでしょう。
現代では、ヨガのエクササイズとしての要素が注目されていますが、本来は精神面の安定が重要な目的のひとつでした。
そのために、腹式呼吸が利用されてきたということのようです。
腹式呼吸をやる時のポイントと注意点

呼吸は意識せずに行っていますが、腹式呼吸をやるときは、意識して呼吸することが必要です。
ヨガで呼吸法の練習をするときは、「安楽座」とよばれる座った姿勢で行います。
骨盤を立てて、背筋を伸ばして座ることを意識しましょう。
腹式呼吸をするときは、首や肩に力が入らないよう注意することが重要です。
ヨガの腹式呼吸は、鼻呼吸です。
鼻から吸って、鼻から吐きます。
鼻呼吸の方が口から吸うより息をたくさん取り込めるためです。
腹式呼吸では、息を吸ったときにお腹が膨らむよう意識します。
通常の呼吸よりもゆっくりと、これ以上吸えないというところまで吸いましょう。
このとき、肩が上がらないように注意してください。
吸いきったらゆっくりと鼻から吐き出します。
息を吐くときはお腹がへこんでいくのを感じましょう。
一気に吐き出さず、少しずつゆっくりと吐き出します。
体内から悪いもの、不要なものを出していくイメージで、最後までしっかりと吐ききってください。
副交感神経が刺激されるのは、息を吐くときですので、息を吐くことは重要です。
心の中で数を数えながら、吸うときと同じだけの時間をかけて吐ききるとよいでしょう。
腹式呼吸をするときは、おへその5センチほど下にある、「丹田」と呼ばれる場所を意識して行います。
呼吸に合わせて丹田の部分がふくらんだり、へこんだりしているかどうかで判断しましょう。
慣れないうちは、丹田に手を置いて確認するとわかりやすいです。
丹田は、インナーマッスルがある場所です。
丹田を意識して呼吸することで、インナーマッスルも鍛えられます。
腹式呼吸と副交感神経のメカニズムまとめ

ヨガの基本となる腹式呼吸は、息を吸う時にお腹がふくらみ、息を吐くときにお腹がへこむ呼吸の方法です。
ヨガでは、心と体を結びつけ、整える方法として腹式呼吸が取り入れられています。
息を吸う時も吐く時もゆっくりと行うことで、通常の呼吸より深い呼吸となります。
腹式呼吸によって副交感神経の働きが高まり、リラックスできるでしょう。
副交感神経の働きを高めて自律神経のバランスを整えられます。
息を吐く時に副交感神経が刺激されるので、吐く息を意識することが重要です。
腹式呼吸は、普段の呼吸とは方法が違うので、最初は難しく感じるかもしれません。
ヨガのポーズをしながらだと、よけいに難しいですよね。
動くことに気をとられていると、呼吸は浅くなりがちです。
ヨガのレッスンでは、呼吸法の練習があります。
瞑想の時間もありますので、呼吸に意識を向けられるときに少しずつ練習して感覚をつかむとよいでしょう。
腹式呼吸の効果は、これまでに述べたようなリラックス効果だけではありません。
深い呼吸で全身に酸素がいきわたることで、血行がよくなります。
血行促進は、冷えの解消や肩こりの改善につながる効果です。
ゆっくりと呼吸を行うことで、心肺機能が強化されます。
丹田の動きを意識して呼吸することでインナーマッスルが鍛えられ、基礎代謝が上がるので、ダイエット効果も期待できるでしょう。
ヨガのポーズを行う時は、呼吸と動きを連動させることでポーズが深まります。
リラックスした状態の方が体の柔軟性が高まるからです。
呼吸に合わせてポーズを深められるようになれば、無理なく柔軟性を高められます。
寝る前に腹式呼吸をするのもおすすめです。
腹式呼吸で副交感神経を優位にすることで、体に休息のサインを出して睡眠の質を上げられます。
腹式呼吸を何回か行うだけでも、睡眠の質は改善できます。
腹式呼吸だけでもいいですが、ヨガのポーズを一緒に取り入れてもいいでしょう。
ヨガで腹式呼吸をマスターして、心身ともに健康になりたいですね。